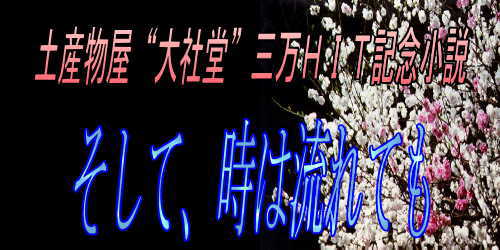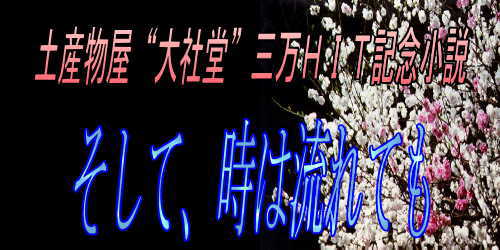……そして、時は流れて。
いつか私は一人になるのかもしれない。
其の一
「──やだっ! もうこんな時間じゃない!」
慌てふためいた少女の声と同時に、どたばたと階段を下りていく音が轟いた。
「舞花さん! 着物、変じゃない? 似合ってる?」
「大丈夫、大丈夫。ただ、あんまりその格好で走ろうとしない方がいいわよ」
「それは由美さんには無茶な注文じゃないですかねえ」
「どういう意味よ!」
階下から聞こえてくる会話を耳にして、壬生風斗は額を軽く揉んだ。
彼の幼なじみの性格は年を経てもほとんど改善されず、むしろますます手がつけられなくなったような気がする。それに自分の気苦労も、だ。
「まったく……」
「苦労してるな、壬生先生」
「からかわないで下さいよ、瀬川さん」
新品のスーツに身を固めた、優しい顔立ちの少年──いや、もはや青年といっていいであろう彼は、ソファーに腰掛けている中年男性を睨んだ。
もっとも、無精髭を生やしたその男は気にする様子もなく、軽く肩をすくめるだけだった。
「事実だろ?」
「それはそうですけど……」
「だったら、もっとしっかりしろよ。お前がこれから相手にするのは、小さい由美ちゃんが20人なんだぜ」
「……その表現、勘弁してください」
今日は彼、壬生風斗と幼なじみの榊由美が通っていた大学の卒業式だ。
風斗は今年の4月から母校の小学校に赴任することが決定している。既に研修で散々な目に遭っているだけに、中年男──瀬川の台詞には反論すら思いつかなかった。
「しかし……早いもんだな」
空のグラスを弄びながら、瀬川が呟く。手にはしているが、彼は好物の酒を一滴も口にしていない。
「お前さんも社会人の仲間入りだ。ガキの頃から見てた、お前がなあ」
「瀬川さん……」
口元に浮かぶ微苦笑が、ちくりと風斗の胸を刺した。
瀬川だけではない。ここ──土産物屋"大社堂"に関わる多くの者が、幼い頃の風斗を知っている。今と変わらぬ姿で、ずっと見守ってきてくれた。
それはとても嬉しく、だが何故か寂しくも思える。そう考えてしまうのは、やはり風斗が半分だけでも"人間"だからかもしれない。
「……これからも、見ていてくれるんでしょう?」
「馬鹿。甘えるな」
少し弱気になった途端、鼻で笑われた。
「俺も元々は一箇所に留まる性分じゃないしな……いつここを離れたっておかしくない」
「大社堂は……麗子さんはどうするんですか?」
「……"俺たち"はそういうもんさ。みんな承知してる」
現実問題、戸籍や人の記憶といったものが"彼ら"を長い間同じ場所に居続けることを拒む。
それは否定できない、冷たい現実。
頭の中では理解していながら、つい仲間たちのことを言葉に出してしまった自分を風斗は責めた。
「……すいません」
「ま、気にするな」
元気を無くしてしまった風斗を見て、瀬川は苦笑した。
「しばらくはまだ、のんびりやらせてもらうさ……何だかんだあっても、ここは居心地がいい」
「──本当ですか!?」
「嘘ついても仕方ないだろ。ほれ、そろそろ由美ちゃんをエスコートしてこいよ」
「はい!」
「……やれやれ……ああいうところは、まだまだ子供だな」
瀬川圭二郎はあっという間に元気になった風斗を送り出した後、1人きりになった部屋で目を閉じた。
静かだ。時折聞こえる階下の声や、外から聞こえる鳥たちのさえずりも、瀬川とは遠いところで発せられたもの。彼は今、ここに1人きりだ。
思えば自分は、そうした孤独にこそ安らぎを覚えていたものだった。
「…………」
長い……とても長い時間、人の一生を遥かに越えた長い時の果てに、瀬川はこの"大社堂"にいる。そして今、1人の人間の門出を祝う場に立ち会っている。
不思議なことだが、瀬川でもこれほど長く──およそ23年だ──人間と付き合ったことはない。
「不思議なもんだ……本当に……」
何より、もっと不思議なのは。
これからも彼や彼を取り巻く人間たちを見守ってやりたいと思っている瀬川自身の心だった。
其の二
「ふーん……じゃあ、クロっちも北海道行くの?」
「……さあなぁ」
土産物屋"大社堂"の裏庭では犬種の分かりにくい、どこか狼にも似た風貌の黒い犬と、赤いタイトな服装をまとったショートカットの女性が"話して"いた。
「まー、拓矢君が獣医になるのは分かってたことだし、ね」
「オレは……大社堂にいた方がいいのか?」
黒い犬──クロが寝そべりながら、首だけ動かして女性を見つめた。
女性の方は縁側に腰掛け、陽光を気持ちよさそうに浴びている。なかなかの美女だが、そうした仕草は気取った様子がまるでない。
「別にいいんじゃないの? ネットワークっていっても、そんなに強制力があるわけでもないし。クロっちの好きなようにするのが一番でしょ」
「うん……」
黒犬クロの目下の悩みは、大学受験を控えた友人・阿部拓矢の進学問題である。出会った頃は小学生だった少年も成長し、今では高校生だ。家が獣医だし、何より拓矢自身が動物好きなので、進学志望も獣医学部一本。そういう意味では、阿部家の方では何も問題はない。
だが問題は──拓矢の希望する大学が、北海道にあることだった。本州のほぼ中央に位置する長野県諏訪市から、海峡を一つ飛び越えた先にある北の地へ。犬のクロでなくても、その距離はあまりに遠い。
「ホカイドーって、遠いのか?」
「うん。日本じゃないもん」
「!? そ、そうなのか!?」
慌てるクロを見て、女性──日羽茜は内心ほくそ笑んでいた。
元々が犬という出自に縛られているクロは世間の常識というものを知らないから、からかうには絶好のカモだ。
「そりゃーもう、遠いなんてもんじゃないわよ。途中で砂漠を越えなきゃいけないし、戦争が起こってる場所もあるし」
「そ、そんなところにタクヤ、べんきょーしにいくのか!? だ、ダメだ!!」
「んー、でも、拓矢君もそれは覚悟の上なんだろうし」
「うううううーーーーー」
悩んでいるクロの姿は少し滑稽で、茜は痛むわき腹を抑えて必死に笑いをこらえる。
「どうする? 北海道、行く?」
「……」
クロは考えながら、無意識に鼻をひくひくと動かす。
知能は人間と変わらないクロだが、行動は犬と同じだ。だから彼は、視覚より嗅覚・聴覚を感覚の主体にしている。
今感じるものは、高地に位置する諏訪地方ならではの爽やかな空気。
小さな敷地に生い茂る草木の匂い。
表通りから離れているため喧騒とも無縁な、穏やかな空間。
ここに来る度にクロは思う。
(大社堂って、キモチのいいところだ)
クロにとって、ネットワークという存在は別に重要ではない。いざとなればクロは一匹でも生きていけるし、他の誰かの生き方になんて興味もない。
クロはただ、牙を剥く自分を優しく抱きしめてくれた人間の少年を守りたかっただけだ。その結果として"大社堂"の存在を知り、自分と同じ者たちと出会った。言ってしまえば、それだけだ。
けれど。
心のどこかで、拓矢に対する気持ちとは別の気持ちがクロを迷わせる。
"大社堂"から離れたくないクロがいる。この"キモチのいいところ"を失いたくない──そんな風に考えてしまう。
(じゃあ、タクヤは……タクヤがオレの一番"キモチのいいところ"だけど、タクヤは……)
考えてみる。
大切な友達の、大切なものを。
(うーん、イイ顔してるね、クロっち。手元にカメラないのが惜しいよ)
自分の職業的必需品を2階に置いてきてしまった事を悔しく思いつつ、茜は黙ってクロを見守っていた。この子も成長してるんだな、と嬉しさを感じながら。
内に秘めた戦闘能力は"大社堂"で最も優れていると言っていいクロだが、その精神は幼い。最初の頃は、半ば子供を育てるような感覚で付き合っていたのを茜はよく覚えている。もっとも茜と瀬川はいい加減なことを教え込んでばかりで、風斗のように真面目な面々はかなり苦労していたようだ。
(……それに比べると、私はどうかなあ)
天空にある一族の隠れ里を飛び出し、人間の世界へやってきた自分。
愛する人間と出会い、別れ……そして麗子たちと出会うことになった。"大社堂"に入ってからも自由に生きてきた。
やがてある激しい戦いの結果、死んだはずの彼は茜と同じ存在になって帰ってきた。様々な障害はあったが、2人は再び想いを通じ合わせることができた。
だが──それだけだ。
根本的な部分で、茜は自分とクロがよく似ていると感じる。どちらもたった一人の、かけがえのない人間と出会い、それが自分の心の大きな場所を占めているという点だ。
無論、"大社堂"の仲間たちも大事に思っているが、彼女たちにはそれ以上に大切にしたい者がいて、いざとなればその絆のために他の全てを捨ててもいいという覚悟がある。
けれど、その覚悟が自身を留めてしまっているような気がしてならない。
(クロ以上に、私には"大社堂"にいる理由がない……)
友情? 義務感? 恩義?
どの言葉も茜の心にはしっくりと当てはまらない。
「……アカネ、元気ないぞ?」
「そう?」
さらっと笑みで答えを返しながら、茜は内心で冷や汗を拭っていた。
クロの嗅覚は犬のそれより数段優れ、感情まで察してしまう。とはいえ、今の微妙な心の揺らぎまで気づかれるとは思わなかった。
追及を逸らすため、茜は先程の質問を続けた。
「で、決まった? 北海道へ行くかどうか」
「うーん……ムズカしいけど、オレ……ここにいるかもしれない」
予想外の答えだった。
クロなら、拓矢と一緒に北海道へ行くと思っていたのだが。
「どうして?」
「それは、えーと……ベンキョーが終われば、タクヤはこっちへ帰ってくるんだろ? だったらオレ、こっちでミツルやスズハを守ってなきゃ。キモチのいいところがなくなってたら、オレはイヤだ……タクヤだってきっと、サビシいって思うから。だからオレ、守らなきゃ」
「……そっか」
たどたどしい言葉の中に込められた、クロの真っ直ぐな想い。
茜はそれを微笑ましく思いながら、自分の中で足りなかった答えをを見つけ出していた。
「私も……守らないとね」
「? 何をだ?」
「ここよ。私が今いる、この場所。"キモチのいいところ"を」
一度、故郷に帰ろう──茜は心ひそかに決意を固めていた。
自分はまだ何も決着をつけていない。なぜ隠れ里を飛び出し、人間と共に生きようとしたのかを。好奇心だけではない
数百年間の想いが、茜の心にある。
彼女が一番"キモチのいいところ"を見つけるには、彼女が生まれた始まりまで戻らなければいけない。まだ何も知らなかったあの頃の自分自身に、そのことを伝えるために。
そして、そこからようやく茜は自由になれるはずだ。
「……"ここ"じゃないのか?」
「え?」
ふにゅっ。
一瞬の隙をついた後の、奇妙な感触。
起き上がったクロが縁側に前足を置いて立ち上がり、茜の胸を鼻で押したのだ。
「──!!!」
「セガワが言ってたぞ。オンナは"ここ"が"キモチのいいところ"だって」
「…………あのスケベ中年……っ!!!!」
「? 間違えたか?」
「二度もするなーっ!」
怒りに震える茜の拳が、クロの頭頂部に炸裂した。
其の三
「……何だか騒がしいですねえ」
裏庭の方へ視線を向けながら、青年──野牟田広はのんびりと茶をすすった。
今日もいつもと変わらない屋号の入った半纏を羽織り、少々肉付きが良すぎる顔は幸せそうだ。
「はぁ〜……平和が一番ですねえ」
「お代わり、いります?」
「あ、これはどうも」
腰ほどまである長い黒髪の女性が差し出した急須に、野牟田は湯飲みを差し出した。
溢れる湯気と茶の香りが、静かな空間に微かに漂った。
「……ふぅ」
身体の隅々まで暖まっていく感覚が、この上なく心地いい。
野牟田は満足そうに何度も頷きつつ、目の前の女性へと視線を向けた。
20代半ばの、物静かな女性だ。今時珍しい楚々とした雰囲気で、お茶の飲み方にも気品に似たものが感じられる。
良家のお嬢様といっても十分に通じるだろう。
だが、今の彼女にはどこか明るさが欠けていることに野牟田は気がついていた。
「舞花さん、今日は遠慮してもよかったんですよ。……風斗君も由美さんも、無理せずにと言ってましたし」
「いえ……大丈夫です。お爺様も節目の日だから行くように、と」
「そうですか……」
気丈に答えつつも、女性──紫苑寺舞花の表情は苦悩に満ちている。
皮肉なことに、その翳りが彼女の儚げな雰囲気をより際立てせてしまっているが。
しかし、野牟田は知っている。
舞花に似合うのは、悲しみの表情ではなく笑顔だ。
「近いうちに"大社堂"は規模を拡大し、再編成をすることになると思います」
野牟田が湯飲みを置き、これまで言いかねていた話題を口にした。
「これまでの秋宮店と本宮店の他に、瀬川さんの探偵事務所を拠点にする予定です。それにより舞花さんは探偵事務所の方に所属してもらうことになりますので……」
「──私は」
顔を伏せたまま、舞花は野牟田の台詞を遮った。
「舞花さん……?」
「私は……"大社堂"を出るかもしれません」
しん、とその場が静まり返った。
舞花は考えをまとめるかのように、ずっと押し黙っていた。
「……そうですか。彩雲さんの具合はそこまで……」
「ええ……」
舞花を養女として受け入れた老人は高齢ながら元気な生活を送っていたのだが、ここ数ヶ月ほど前から体調を崩し、床に伏せる日々が続いている。生命そのものの終わりが近づいていることは間違いなく、舞花も覚悟はしていた。
彼らの同族の中には、病気を癒せる者や若返りの術を習得している者もいる。だが、彩雲はそうした異能の力による救いをきっぱりと断ったのだ。
「お爺様が亡くなれば、紫苑寺家も途絶えます。その先、どうすればいいか……私にはまだ……」
親しい人との別れを前にして、舞花は動揺を隠せずにいた。
野牟田もそうした別れを味わったことがあるから、今の彼女の気持ちは痛いほど理解できた。嘆き、悲しみ、運命への理不尽な怒り……そして何もできない自分への悔しさ。
「……人間は……強いのね」
不意に舞花が、ぽつりと洩らした。
「命が終わること……すべてが消えてしまうことを受け入れるなんて、私にはできない」
「受け入れたわけではないでしょう」
野牟田の穏やかな口調が、珍しく速さを増した。
誤解させてはいけない──そう感じたのだ。舞花の心の拠り所として、老人の存在は大きい。それゆえに、悲しみが心を歪めてしまいかねない。
「死を受け入れることができる者はいませんよ。どんな人間でも、或いは僕らのような者にも……死という終わりはそれだけ大きなものなんです」
「じゃあ、なぜ……お爺様は……」
「……」
野牟田は密かに思う。
彩雲が頑なに異能の治療を拒むのは、舞花に自分との別れを経験させるためではないのだろうかと。大切なものを失う悲しみを知らなければ、新しい出会いは生まれないのだから。
(ですが……その悲しみが大きすぎれば、出会いの時さえ訪れないかもしれない……)
それだけが不安だった。野牟田もできるだけ彼女を支えてやりたいと思うが、最後に頼りになるのは舞花自身の心の強さなのだ。
こういう時、野牟田は世間と隔絶した暮らしを送っている自分に後悔を覚える。心情を察することはできても、助ける方法を思いつけないことに。
「なぜ、なんでしょうね」
野牟田は湯飲みを両手で包み込みながら、呟いた。
生命には終わりがある。けれど、自分たちには終わりがなく、望めば悠久の時を生き続けることができる。出会いと別れは無限のように訪れ、その度に喜びと悲しみを抱いていく。
そしていつしか、そうしたことに慣れてしまった自分がいる。だが、舞花は──。
「……私はお爺様の傍で生まれ、お爺様と生きて、お爺様の手の中で一度は永い眠りについて……」
自らの胸の内にある思い出を紐解くように、舞花は瞳を閉じた。
「そして再び目覚めた時、お爺様は私を待っていてくれた……。お爺様は……私にとってとても大切な人。でも私がお爺様を待つことはできない……もう永遠に帰ってこないから」
「舞花さん」
どうしようもないことだ。彩雲は人間で、舞花はそうではない。
しかし、たったそれだけのことが、深く大きな溝となって2人を隔てている。あまりにも哀しい現実。
負けたくない──そう思いながらも、舞花の心は哀しみに引き裂かれそうになってしまう。立ち向かおうとする気持ちが濃い闇に飲まれていきそうになる。
「駄目よね、こんなことじゃ……」
「いいじゃないですか」
苦悩に満ちた表情の舞花に向かい、野牟田は力強く答えた。
「僕らは人を遥かに越えた力を持っています。ですが、だからといって心まで人とかけ離れたものにしてしまう必要はありませんよ。喜んだり、悲しんだり、怒ったり、笑ったり……それでいいじゃないですか」
「野牟田さん……」
「舞花さんの悲しみは、舞花さん自身が向き合わなければいけないことですけど……一つだけ覚えておいてください」
野牟田はいつも通りゆっくりと、心に沁み込むように穏やかに語った。
まるで願いを込めるように。誰かに祈るように。
目の前にいる仲間を励ますために。
「あなたがいなくなれば、悲しむ仲間がここにいます──それだけは、忘れないで下さい」
「……はい」
頷いた舞花の頬を、一粒の涙が伝い落ちる。
けれど、彼女の表情にはほんの少し……明るさが取り戻されていた。
其の四
「あーあ、麗子さん何やってんだろ?」
露骨につまらなそうな態度を表に出しているのは、中学生くらいの小柄な少年だった。
大きめのパーカーとハーフパンツ姿。生意気そうな顔つきは、今は不満で膨れ上がっている。
「もうすぐ時間だぜー。ったく、ホントにのんびりしてるよなぁ」
「大丈夫ですよ。車の準備は済んでますし」
そう答えたのは、エプロン姿の女性。大人しそうな雰囲気だが、今は店舗の掃除をしているせいかキビキビと動いていた。
綺麗好きな女性らしく、随分と本格的にやっている。
「渚姉ちゃん、いつまで掃除すんの? ていうか、大社堂全部掃除する気?」
「え? 駄目です?」
「……」
あまりにも普通に答えられてしまっては、少年──綱守薫としても呆れるだけだ。
「今日は風斗と由美の卒業式の見物なんだからさ、別にそこまでしなくても」
「んー、でも気になっちゃって。ほら、この汚れなんて気になりません?」
「ならないって」
ふう、と大袈裟に溜め息をついて薫は天井を見上げた。
大社堂はおそろしく年季の入った木造建築だから、使われている木材はその年月を示すかのように黒ずんでいる。が、決して汚くは見えない。むしろ歴史の重さのようなものが視覚化され、自分たちを取り巻いている気がした。
(歴史……時間の流れかぁ)
薫は心の奥で、うまく言い表せない気持ちを感じた。
それは今日の見物に乗り気になれないことと関係しているような気がして、薫としては何とも落ち着かなかった。自分で自分の気持ちが分からない──そんなことはこれまで滅多になかったのに。
すると、彼を何気なく見つめていた女性──古澄渚が、小さく微笑む。
「薫君、淋しいんですか?」
「……は?」
「だって今、すごく淋しそうな顔をしてましたよ」
「ンなわけないじゃん」
渚の言葉を、薫は笑いながら一蹴する。
「淋しい」などという単語自体、自分とは無縁のものだ。使役されるものとして生まれ、それからずっと誰かに仕えてきた。自由な意志を束縛されることはなかったが、傍にいることは自然な前提として薫の心にあった。だから彼は孤独を知らず、淋しさを感じることがない。
いや、正確に言えばよく分かっていないのだ──淋しさという感情が。
「でも、元気がないです」
珍しく渚は引き下がらず、言葉を続けた。
「いつもの薫君だったら、ここで麗子さんを待ってなんかいません。すぐに見つけ出して連れて来ちゃうと思います」
「……そりゃ、そうだけど」
微妙に褒めているか皮肉を言われているか分からず、薫は苦笑した。彼女の性格からして皮肉だとは思えないが。
「でも薫君はさっきからここで待ってます。それって……」
「もう、いいってば。ストップ」
渚を制止するかのように、両手を前に出してみせる。
このままだと自分にも見えていない部分まで触れられてしまいそうで、薫は少し怖かったのかもしれない。もちろん、そんな弱気な気持ちを表に出すことは無いけれど。
「渚姉ちゃんも意外に言うねー」
「そうですか? ……だとしたら、薫君って弟みたいな感じだからかも」
「弟……」
実のところ見た目は中学生くらいでも、生きてきた年月は渚を遥かに上回っている。
渚もそのことを知っているのに。
複雑な表情を見せる薫に対し、雑巾を絞りながら渚は言った。
「薫君はたぶん何でもできて、1人でも大丈夫なんだろうけど……私たちから見ると、そうじゃないですよ」
「それって、見た目のせい?」
「いいえ」
渚は微笑みつつ、彼の問いに首を振る。
「心──なのかな」
「……こころ?」
「薫君は大社堂の皆さんのこと、好きですか?」
「は?」
唐突な質問に、薫は目を丸くした。
「好きですか?」
「……いいじゃん。そんなの、どっちだって」
「やっぱり」
戸惑って、言葉を濁して、そしてそっぽを向いてしまった少年を見つめる。
渚は彼とは違い、自我というものが早い段階で確立していたから、何となく薫の抱く戸惑いを理解していた。
「薫君は……きっと大社堂へ入ってきてから、そのままなんです。自分が大社堂の仲間だって気持ちに、しっかりとした自信がもてないから……だから、そんな風に答えちゃうんです」
「……」
「今も元気がないのは、成長してる風斗君や由美さんを見て──」
「だから、もういいってば!」
思わず大声で叫んでしまったことに何より驚いているのは、当の薫本人だった。
気まずそうに顔を背ける彼に、渚はそっと近づいた。
「……ごめんなさい」
渚は後ろから薫の肩に手を置いて、呟いた。
不用意な言動だったと、彼女自身も悔やんでいる。けれど渚は自分の不器用さを知っているし、下手な大人よりずっと冷静な目をもつ薫相手に、小手先の言葉が通じるとは思えなかった。
「私、駄目ですね……麗子さんたちみたいに、上手く言葉にできなくて……」
「……」
「でも私……嬉しいです。薫君、いつもからかうような言い方ばかりですから」
「……オレは、さ」
薫がようやく口を開く。彼にしては珍しく歯切れの悪い口調だったが、渚はそれを黙って聞いた。
「オレは、ずっとこのままでいいや、って思ってた。その方が面倒臭くないしさ……。でも、大社堂に来てからは何だか違ってきて……みんなが羨ましいような気もしてさ」
変わっていく現実。実感する時の流れ。
一歩離れた位置で見つめていた薫にすれば、その一歩こそが何より重要で困難な代物だった。変わってみたいという好奇心と、未知の経験を拒む臆病さが薫の心を中途半端な位置で立ち止まらせている。
「でもって、ここにきて風斗は就職するし、クロも拓矢についていきたがってるし……じゃあ、オレはどうなのかなー、とか考えちゃって──あ〜、オレ何言ってんだろ」
喋っているうちにますます混乱したのか、薫は乱暴に頭を掻く。
そんな様子に微笑みつつ、渚は言った。
「私は、大好きですよ」
「……は?」
「薫君のこと……大社堂の皆さんのこと」
「あ、あはは……」
迷いの無い言葉。純粋な想い。
さしもの薫も得意の毒舌を振るうことさえできず、曖昧に笑うしかなかった。
(やっぱり、こういうのは苦手だ)
すぐには変われそうもないし、その気もあまりない。結局、面倒なのは確かなのだし。
けれど。
「オレもまあ……キライじゃない、かな」
「はい」
今は、これで十分だと薫は思った。
そして渚も、笑顔でその答えを受け入れた。
其の五
……風が吹いた。
真樹麗子はその中に1人佇み、瞳を閉じていた。
どこか人間離れしていると言ってもいい、完璧な美貌の持ち主だった。緩くウェーブのかかった髪は緑がかっているようにも見え、彼女に神秘的な雰囲気を与えている。
麗子の眼前にあるのは、一本の巨木。
高さ十数m、周囲5m近くはありそうなモミの木だ。幹の部分には注連縄が巻かれており、全ての枝葉が切り落とされたこの樹を唯一守っている。
「長かったわね……」
そっと手を伸ばし、幹に優しく触れる。年老いた大木からは、生気がほとんど感じられない。
麗子はそのことに悲しみを覚えながら、静かに微笑んだ。
「ご苦労様……本当に、ありがとう」
「──時間だぞ、麗子」
背後から届いた声に、麗子はゆっくりと振り返った。
片手をポケットに突っ込んだまま歩いてくるのは、瀬川圭二郎だ。木の葉が舞い落ちる場所だというのに、彼の足音はまったくしない。
しかし麗子は驚きもせず、その微笑を彼にも向けた。
「ごめんなさい。少し考え事をしていたから」
「まあ、いいけどな。うちの連中は何やら騒いでいたし」
「あらあら、困ったわねえ」
麗子の微笑みが苦笑へと変わり、人間離れした美貌にも親しみが増す。
瀬川は彼女の隣まで来ると、眼前の巨木を見上げた。
「……済んだのか?」
「ええ。私はもう、今ここにいる"私"だけ」
この巨木は"御柱"──長野県諏訪地方で七年に一度執り行われる御柱祭で使われる御神木。そしてこれまでの間、この樹こそ麗子の本体であった。祭りにかける人々の、篤い信仰心などの強い"想い"が"御柱"を人ならざる生命の形──妖怪にしたのである。
麗子の本体は、始まりの御柱の一柱。その頃の記憶や心は、ある事情でほとんどを失ってしまったが、麗子はさほど気にしていない。今、ここにいる自分が、自分自身だと信じているから。
「すまんな」
瀬川がさり気なく詫びると、麗子は小さく首を横に振った。
「いいのよ。例の事件は、きっかけに過ぎなかったと思うわ。いずれ私がそうしていたかもしれないから」
例の事件とは、2000年に起きた"神"との戦いに関連したものだった。
諏訪地方に存在する謎めいたエネルギー"龍"を悪用しようとした天使たちと、麗子たち"大社堂"の妖怪たちは激しい戦いを繰り広げたのである。
様々な苦難があったものの、"大社堂"は勝利した。しかしその戦いの最中、麗子は天使の策略によって必要以上の生命エネルギーを本体である御柱に注ぎ込まれ、自己崩壊を起こしかけたのだ。
「あの時は、こんな方法しか思いつかなかったが……」
「選んだのは私よ、瀬川くん」
絶望的な状況下で瀬川が見いだしたのは、本体と分身を完全に切り離してしまうことだった。
そうすれば自分の力を失わずに、余剰したエネルギーの影響を受けずに済む──結果として、その儀式に2年近くも費やしてしまったのだが。
「この樹も本当に頑張ってくれたわ……」
「こいつは、枯れちまうのか?」
「そうね……でも、それは当たり前のことなのよ。生命は……そうやって流れていくものだから」
「……ああ」
だが、と瀬川は思う。
生命が流れていくものだとしたら、自分たち妖怪は何なのだろうと。
瀬川ほど長命な妖怪でも、その答えを見つけ出すことができずにいる。ほぼ永遠といえるだけの生命を持つ、"想い"から生まれた存在。闇と影に潜む、幻の世界の住人。
けれど、そんな自分たちにも確かに心はある。"想い"はあるのだ。
それは生命ではないのだろうか?
「なあ、麗子」
「なに?」
視線を動かさぬまま話し出した瀬川を、麗子はちらりと見つめた。
「俺は……ここにいていいか?」
その問いに、麗子はどこか寂しそうな、それでいて優しさに満ちた表情で答えた。
静かに、はっきりと。
「私は、ここにいるわ」
たった一言。
瀬川は少し驚いたように彼女を見た後、悔しそうに頭を乱暴に掻いた。
思えば自分は麗子を支えているようでいて、肝心な時には彼女に支えられてばかりいる気がする。互いの存在に甘えるつもりはないが、心のどこかを確かに預けあっている。
「やれやれ……こりゃ、風斗のことを笑えんか」
「なんのこと?」
「気にするな。さ、行くぞ」
どこか照れも混じった勢いで、瀬川は足早に去っていく。軽く溜め息を吐きつつ、麗子もその後を追う。
と──。
その途中で、彼女の足が止まる。
振り返った麗子の唇が、小さく動いた。風が、その言葉を運んでいく。
「さようなら……また、会いましょう」
そして──。
麗子はもう、振り返ることなく歩いていく。
かつてのもう1人の彼女は、その後ろ姿をずっと見送っていた。
その身を、風に優しく抱かれながら。
其の六
「麗子さーん! 早く早く! もう時間だってばー!」
「せっかちですねえ」
「あっ、私、エプロン着けたままですぅ」
「なー、ホントにオレも行くわけ? ゲーセン行こうと思ってたのにさ」
「そういう子には烈火弾決定♪」
「……そ、それは止めた方がいいんじゃ……」
「まったくもう……あまり騒ぐと人目につくわよ」
「とっくに目立ってるぞ」
みんなが、いる。
「さあ、行こうぜ……麗子」
差し出された手は、私を見守ってくれる仲間たちの"想い"。
だから、私は手を伸ばした。
「あらあら、困ったわねえ」
そして、時は流れても。
私たちは、ここにいる──"大社堂"に。
──「そして、時は流れても」 終わり
© 1997 Member of Taisyado.