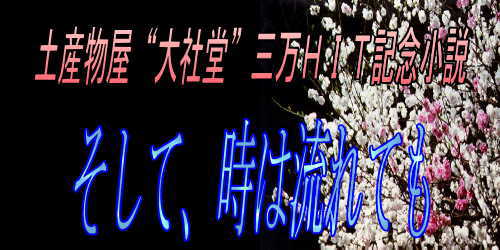
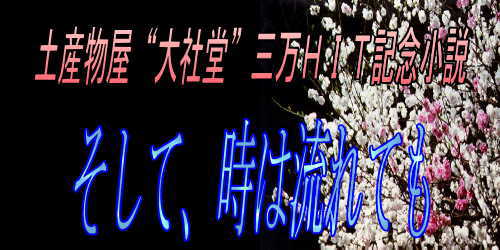
……風が吹いた。
真樹麗子はその中に1人佇み、瞳を閉じていた。
どこか人間離れしていると言ってもいい、完璧な美貌の持ち主だった。緩くウェーブのかかった髪は緑がかっているようにも見え、彼女に神秘的な雰囲気を与えている。
麗子の眼前にあるのは、一本の巨木。
高さ十数m、周囲5m近くはありそうなモミの木だ。幹の部分には注連縄が巻かれており、全ての枝葉が切り落とされたこの樹を唯一守っている。
「長かったわね……」
そっと手を伸ばし、幹に優しく触れる。年老いた大木からは、生気がほとんど感じられない。
麗子はそのことに悲しみを覚えながら、静かに微笑んだ。
「ご苦労様……本当に、ありがとう」
「──時間だぞ、麗子」
背後から届いた声に、麗子はゆっくりと振り返った。
片手をポケットに突っ込んだまま歩いてくるのは、瀬川圭二郎だ。木の葉が舞い落ちる場所だというのに、彼の足音はまったくしない。
しかし麗子は驚きもせず、その微笑を彼にも向けた。
「ごめんなさい。少し考え事をしていたから」
「まあ、いいけどな。うちの連中は何やら騒いでいたし」
「あらあら、困ったわねえ」
麗子の微笑みが苦笑へと変わり、人間離れした美貌にも親しみが増す。
瀬川は彼女の隣まで来ると、眼前の巨木を見上げた。
「……済んだのか?」
「ええ。私はもう、今ここにいる"私"だけ」
この巨木は"御柱"──長野県諏訪地方で七年に一度執り行われる御柱祭で使われる御神木。そしてこれまでの間、この樹こそ麗子の本体であった。祭りにかける人々の、篤い信仰心などの強い"想い"が"御柱"を人ならざる生命の形──妖怪にしたのである。
麗子の本体は、始まりの御柱の一柱。その頃の記憶や心は、ある事情でほとんどを失ってしまったが、麗子はさほど気にしていない。今、ここにいる自分が、自分自身だと信じているから。
「すまんな」
瀬川がさり気なく詫びると、麗子は小さく首を横に振った。
「いいのよ。例の事件は、きっかけに過ぎなかったと思うわ。いずれ私がそうしていたかもしれないから」
例の事件とは、2000年に起きた"神"との戦いに関連したものだった。
諏訪地方に存在する謎めいたエネルギー"龍"を悪用しようとした天使たちと、麗子たち"大社堂"の妖怪たちは激しい戦いを繰り広げたのである。
様々な苦難があったものの、"大社堂"は勝利した。しかしその戦いの最中、麗子は天使の策略によって必要以上の生命エネルギーを本体である御柱に注ぎ込まれ、自己崩壊を起こしかけたのだ。
「あの時は、こんな方法しか思いつかなかったが……」
「選んだのは私よ、瀬川くん」
絶望的な状況下で瀬川が見いだしたのは、本体と分身を完全に切り離してしまうことだった。
そうすれば自分の力を失わずに、余剰したエネルギーの影響を受けずに済む──結果として、その儀式に2年近くも費やしてしまったのだが。
「この樹も本当に頑張ってくれたわ……」
「こいつは、枯れちまうのか?」
「そうね……でも、それは当たり前のことなのよ。生命は……そうやって流れていくものだから」
「……ああ」
だが、と瀬川は思う。
生命が流れていくものだとしたら、自分たち妖怪は何なのだろうと。
瀬川ほど長命な妖怪でも、その答えを見つけ出すことができずにいる。ほぼ永遠といえるだけの生命を持つ、"想い"から生まれた存在。闇と影に潜む、幻の世界の住人。
けれど、そんな自分たちにも確かに心はある。"想い"はあるのだ。
それは生命ではないのだろうか?
「なあ、麗子」
「なに?」
視線を動かさぬまま話し出した瀬川を、麗子はちらりと見つめた。
「俺は……ここにいていいか?」
その問いに、麗子はどこか寂しそうな、それでいて優しさに満ちた表情で答えた。
静かに、はっきりと。
「私は、ここにいるわ」
たった一言。
瀬川は少し驚いたように彼女を見た後、悔しそうに頭を乱暴に掻いた。
思えば自分は麗子を支えているようでいて、肝心な時には彼女に支えられてばかりいる気がする。互いの存在に甘えるつもりはないが、心のどこかを確かに預けあっている。
「やれやれ……こりゃ、風斗のことを笑えんか」
「なんのこと?」
「気にするな。さ、行くぞ」
どこか照れも混じった勢いで、瀬川は足早に去っていく。軽く溜め息を吐きつつ、麗子もその後を追う。
と──。
その途中で、彼女の足が止まる。
振り返った麗子の唇が、小さく動いた。風が、その言葉を運んでいく。
「さようなら……また、会いましょう」
そして──。
麗子はもう、振り返ることなく歩いていく。
かつてのもう1人の彼女は、その後ろ姿をずっと見送っていた。
その身を、風に優しく抱かれながら。
© 1997 Member of Taisyado.